自宅を離れるときにはいつも、ある心配ごとが。
留守をしている間に、まるが死んじゃってるんじゃないか。
そんな思いがいつも心にあって、玄関の扉をあけて、眠そうに出迎えてくれるまるの顔をみるまでは、心が休まらないのです。コングを与えて出た日には、まるがバカみたいにフードを吸い込んで食べてしまって、のどに詰まらせて死んでしまうのではないか、とか。夏の暑い日には、エアコンが急に止まってしまい、熱中症で死んでしまうのではないか、とか。
なぜそんな風に、過剰に、しかも異常なまでに心配してしまうのか。これまで深く考えてみたことがなかったのですが、先日、ある本を読んだときに、その理由がわかったんです。その本とは、穴澤賢さんの”また、犬と暮らして”です。
穴澤さんは以前、愛犬の富士丸を不意に失ったんです。数時間の留守のあと、いえに戻ってみたら、富士丸が息を引き取っていたのでした。富士丸はまだ7才だったので、寿命と言ってしまうには早すぎる死だったんですね。だから穴澤さんは、いまでも留守をするとき、いま飼っている犬たちが死んでしまうのでは?という心配が離れないというのです。それは、富士丸の死がトラウマとして残っているのだと。それを読んだとき「あ、わたしの心配事は、コレだったんだ。」と思ったんです。
コレというのも、かれこれ20年以上も前のこと。
1Kのアパートで一人暮らしをしていたころ、うさぎの女の子、うさこを飼っていたのです。籠から出してあげると、部屋中走り回って、そのあとそばにぴたっと寄ってきて、うさぎながらとても私になついていた子でした。でもあるとき、仕事で家を長時間あけて帰ってみたら、そのうさぎが死んでしまっていたんです。長時間留守にしてしまった過失はわたしにありました。あんなにも簡単に、うさこが死んでしまったことが、いや死なせてしまったことが、大きなトラウマとしてずっと残っていたんです。
昔のことで、ときどき思い出すことはあっても、あのときの衝撃とかショックとか悲しみといった諸々の感情を思い出すことはあまりなかったんです。というか、思い出してその感情を生々しく思い出すことに耐えられなかったのでしょうね、思い出すことを避けていたんだと思います。そのためか、それがトラウマとしてこんなにも今にまで尾を引いているとは思ってもみなかったんですね。
自分の過剰なまでの心配性がどこから来るものか。それを理解できた穴澤さんの本に出会えたことに感謝するとともに、穴澤さんの富士丸と過ごした日々をつづった他の本も、読んでみたいなぁと思ったところです。
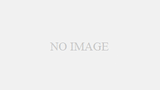
コメント